

「今どき」の若者たちの行動に驚いたという話は絶えず耳に入る。心理学では特に、社会人への移行期間である青年期に関心を寄せたものが、若者たちの心に迫る研究として数多く行われてきた。青年期は初潮や精通を代表とする身体の成熟から始まり、心が成熟し、社会的に責任を負えるようになる時期(就職等)までとされる。青年期の初期(思春期)では、身体の急激な変化に適応することが求められ、そこから青年期後半にかけて、多様な役割の経験を通して職業や生き方の選択をしていく。
モラトリアム(猶予)という用語に象徴されるように、青年たちは比較的自由に自己決定の下で活動することが許されている。感情的に不安定であるがゆえ新しい情報にも敏感で、かつそれを柔軟に取り込んでいけることもあり、価値観の異なる「今どき」の若者の一部として批判の対象にもなりやすい。ただし、それらの批判を授業等で紹介しても、あまりピンとくる学生は少ないようである。「今どき」の様子に敏感に反応し、それを若い世代の特徴だと主張するのは、若者たちを社会に迎える我々上の世代の特徴のようである。多くの大人たちが社会の先行きに不安を感じた時に、新しい若者論が誕生し、若い世代を揶揄(やゆ)するワードや論調が出回るという指摘もあるが、そういった現象は確かにあるのだろう。
青年心理学者の西平直喜氏によれば、青年の心の特徴を捉える際には青年性、世代性、個別性の3つの視座があるという。青年性とは、他の発達段階(児童期や成人期など)との比較から青年期の特徴を探る視点である。一方で世代性とは、先述のような「今どき」に関心を向け、現代青年に特有の心理傾向を探る視点である。また個別性は、個々の青年の育った環境やパーソナリティ・気質等の違いに目を向けることであり、同じ時代に青年期を経験している個々の青年たちの豊かな個性に関心が持たれる。
筆者はこれまで30年弱、主に青年期を対象として調査法による実証的研究を行ってきたが、青年たちの心に時代的な変化を感じたことはあまりなかった。確かに自尊感情が昔より低下していることはデータでも示されているし、対人関係の希薄化も多くの研究で示唆されている。自己実現を職業に求める青年が少なくなったのも事実であろう。ただ、青年たちは変わらず親の価値観から脱却を試み、自分を知りたいと願い、アイデンティティの確立を求めてもがいている。現代青年の心理的傾向は、昔から指摘されている比較的普遍な青年性の視点で十分解釈できることが多いのである。
青年をはじめとする若い世代を、世代性の観点から、自分たちとは異なるものとして関係を断ってしまうことはもったいない。目に見える様子では違えども、青年期を迎えた心は本質的には変わらない。これからの時代、同じ心の仕組みを有した存在として青年たちに一定の関心を持つことが、若者たちとともに社会を作っていく上でますます重要になっていくのではないだろうか。
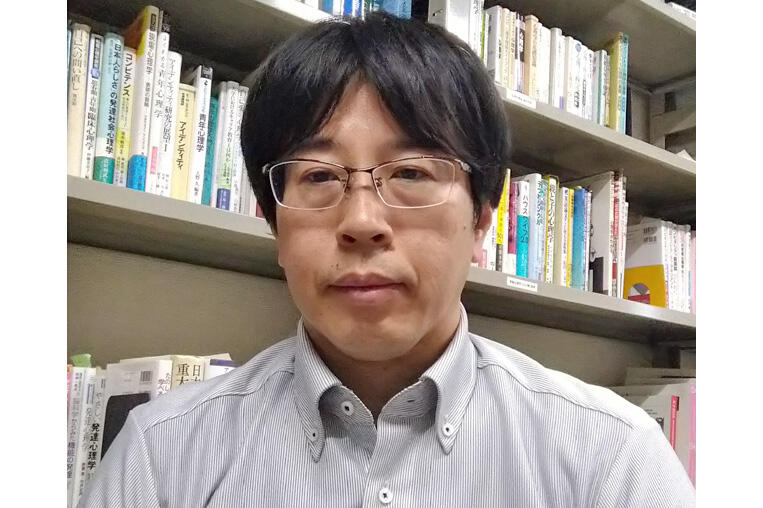
小平 英志 教育・心理学部教授
※この原稿は、中部経済新聞オピニオン「オープンカレッジ」(2025年3月19日)欄に掲載されたものです。学校法人日本福祉大学学園広報室が一部加筆・訂正のうえ、掲載しています。このサイトに掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。